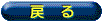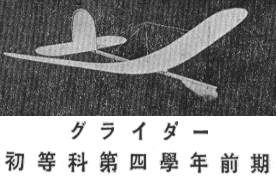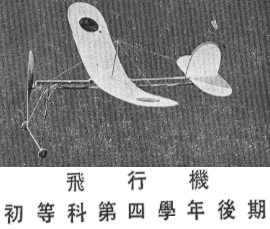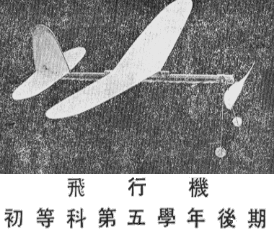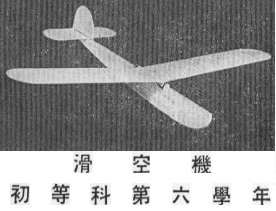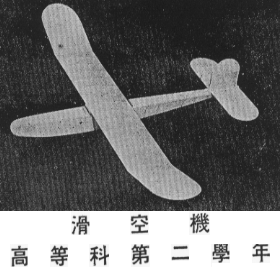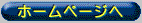当時を偲ぶために旧仮名使いのままの原文で紹介します
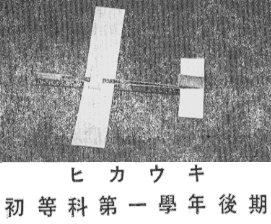 |
ヒカウキ=ヒコウキ
旧仮名使いではこんな言い方をしていました。 テフテフ=チョウチョウ 要旨
中厚紙ヲ主材料トスル簡単ナル切紙滑空機ヲ作ラシメ
且其ノ飛バセ方ヲ指導シテ滑空状態ヲ観察セシメ以テ 航空機ニ関スル親ミト理解トヲ誘起セシム。 飛行指導の一部
1.飛バセ方ハ水平尾翼ニ少シク負ノ取付角ヲ附シタル
後主翼下胴体ヲ持チ水平ヨリ稍々下向キニ適度ノ力 ヲ加ヘテ軽ク押シ出ス様ニナス。
児童ハ一般ニ過度ニ力ヲ入レ或ハ上方ニ向ケテ投
グル傾向アルヲ以テ之ヲ矯正シテ正シキ飛バセ方ヲ 授クルコト。 |
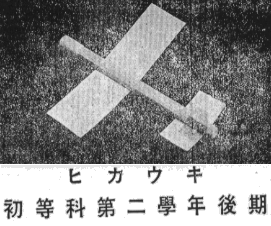 |
要旨 「キビガラ」、中厚紙ヲ主材料トスル簡単ナル小型滑空機 ヲ作ラシムルト共ニ特ニ全体ニ重心ヲ定位置ニ合セル 方法ヲ教ヘ且其ノ飛バセ方及調整ノ方法ヲ指導シ以テ 航空機ニ関スル親ミト理解トヲ深カラシム。 「キビガラ」=トウモロコシの茎の中のスポンジ状の芯を 乾燥させ、着色をして工作材料として使った。 飛行指導の一部 機首ニ古釘ヲ挿入セザル場合(重心後方ニアル場合) 機首ニ古釘ヲ挿入シタル後長キ紙ヲ巻キタル場合 (重心前方ニアル場合)ニ付き実験セシメ最後ニ機首 ノ錘ヲ加減シテ重心ヲ主翼前縁ヨリ翼弦長ニ三分ノ一 ノ位置ニ合セテ其ノ滑空状態ヲ比較観察セシメルコト。 |
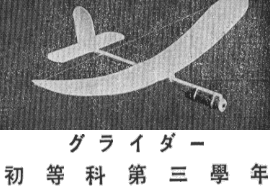 |
要旨 「竹ヒゴ」、細木、薄紙ヲ主材料トスル小型滑空機ノ工作 法ヲ授クルト共ニ之ガ滑空法ヲ指導シテ各部ノ調整方法ヲ 知ラシメ正シキ滑空ニ必要ナル条件ノ大要ヲ会得セシム。 製作指導の一部 錘ハ古釘ヲ「キビガラ」中ニ頭部マデ挿込ミテ作ル。 之ヲ機首ノ下側ニ糊着ケシ糸ニテ縛ル。 主翼ハ胴体ノ基準面ニ取付角ヲ付シテ取付クルコト。 取付角ヲ付スルニハ前縁ノ取付位置ニ当タル部分ニ 枕木ヲ載セ生半紙ヲ巻キテ糊付ケトシ其ノ上ニ前縁ヲ載セル。 |