松島・瑞巌寺五大堂
松島のシンボル・五大堂は、
大聖不動明王を中央に東方降三世明王、西方大威徳明王、 南方軍荼利明王、北方金剛夜叉明王の五大明王像を
安置したことにより、五大堂と呼ばれるようになった。
 大同2年(807年)、坂上田村麻呂が東征のおり、毘沙門堂を建立したのが最初
後に、慈覚大師円仁が円福禅寺(瑞巌寺の前身)を開いた際、現在の建物は、
伊達政宗公が慶長9年(1604年)に再建したもので、桃山式建築手法の粋をつくして完工したもので
伝説では、 慈覚大師円仁が五大明王を安置したところ、坂上田村麻呂が祀った毘沙門天は光を発して沖合いの小島に飛び去り、
その島が毘沙門島と言い伝えられている(国重要文化財)
大同2年(807年)、坂上田村麻呂が東征のおり、毘沙門堂を建立したのが最初
後に、慈覚大師円仁が円福禅寺(瑞巌寺の前身)を開いた際、現在の建物は、
伊達政宗公が慶長9年(1604年)に再建したもので、桃山式建築手法の粋をつくして完工したもので
伝説では、 慈覚大師円仁が五大明王を安置したところ、坂上田村麻呂が祀った毘沙門天は光を発して沖合いの小島に飛び去り、
その島が毘沙門島と言い伝えられている(国重要文化財)

 五大堂に渡る 『 透橋(すかしばし)』
五大堂のある島は藩政時代女人禁制だった、橋脚はあったが橋板はなく幅十五㎝ほどの桟が打ち付けら
れているだけだった、橋の上からすかして海が見える事から「すかし橋」の名がある、女人は渡れなかった
のもわかったような気もします?
五大堂に渡る 『 透橋(すかしばし)』
五大堂のある島は藩政時代女人禁制だった、橋脚はあったが橋板はなく幅十五㎝ほどの桟が打ち付けら
れているだけだった、橋の上からすかして海が見える事から「すかし橋」の名がある、女人は渡れなかった
のもわかったような気もします?
 堂の額「五大堂」も長年の風雨にさらされ見づらい
堂の額「五大堂」も長年の風雨にさらされ見づらい
 日本三景の1つである景勝地・松島の景観上重要な建物である (画像クイックで拡大可)
日本三景の1つである景勝地・松島の景観上重要な建物である (画像クイックで拡大可)
 早朝の静かな五大堂 堂壁面(左上)に十二支の彫刻が施されている
早朝の静かな五大堂 堂壁面(左上)に十二支の彫刻が施されている

 丑 亥
丑 亥

 子 申
堂の周囲に12支が刻まれ太陽の方向と同期していてその時点の時刻を表している
子 申
堂の周囲に12支が刻まれ太陽の方向と同期していてその時点の時刻を表している
 周辺には松島湾遊覧用の観光船発着港が多くある 遠方は福浦橋
周辺には松島湾遊覧用の観光船発着港が多くある 遠方は福浦橋
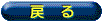
 大同2年(807年)、坂上田村麻呂が東征のおり、毘沙門堂を建立したのが最初
後に、慈覚大師円仁が円福禅寺(瑞巌寺の前身)を開いた際、現在の建物は、
伊達政宗公が慶長9年(1604年)に再建したもので、桃山式建築手法の粋をつくして完工したもので
伝説では、 慈覚大師円仁が五大明王を安置したところ、坂上田村麻呂が祀った毘沙門天は光を発して沖合いの小島に飛び去り、
その島が毘沙門島と言い伝えられている(国重要文化財)
大同2年(807年)、坂上田村麻呂が東征のおり、毘沙門堂を建立したのが最初
後に、慈覚大師円仁が円福禅寺(瑞巌寺の前身)を開いた際、現在の建物は、
伊達政宗公が慶長9年(1604年)に再建したもので、桃山式建築手法の粋をつくして完工したもので
伝説では、 慈覚大師円仁が五大明王を安置したところ、坂上田村麻呂が祀った毘沙門天は光を発して沖合いの小島に飛び去り、
その島が毘沙門島と言い伝えられている(国重要文化財)

 五大堂に渡る 『 透橋(すかしばし)』
五大堂のある島は藩政時代女人禁制だった、橋脚はあったが橋板はなく幅十五㎝ほどの桟が打ち付けら
れているだけだった、橋の上からすかして海が見える事から「すかし橋」の名がある、女人は渡れなかった
のもわかったような気もします?
五大堂に渡る 『 透橋(すかしばし)』
五大堂のある島は藩政時代女人禁制だった、橋脚はあったが橋板はなく幅十五㎝ほどの桟が打ち付けら
れているだけだった、橋の上からすかして海が見える事から「すかし橋」の名がある、女人は渡れなかった
のもわかったような気もします?
 堂の額「五大堂」も長年の風雨にさらされ見づらい
堂の額「五大堂」も長年の風雨にさらされ見づらい
 日本三景の1つである景勝地・松島の景観上重要な建物である (画像クイックで拡大可)
日本三景の1つである景勝地・松島の景観上重要な建物である (画像クイックで拡大可)
 早朝の静かな五大堂 堂壁面(左上)に十二支の彫刻が施されている
早朝の静かな五大堂 堂壁面(左上)に十二支の彫刻が施されている

 丑 亥
丑 亥

 子 申
堂の周囲に12支が刻まれ太陽の方向と同期していてその時点の時刻を表している
子 申
堂の周囲に12支が刻まれ太陽の方向と同期していてその時点の時刻を表している
 周辺には松島湾遊覧用の観光船発着港が多くある 遠方は福浦橋
周辺には松島湾遊覧用の観光船発着港が多くある 遠方は福浦橋