
米子大瀑布全景 (画像クイックで拡大可)
右が「不動滝」85m、左が「権現滝」75mで日本の滝100選にも選ばれている
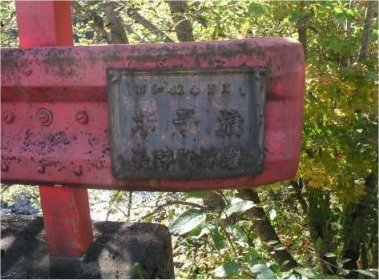
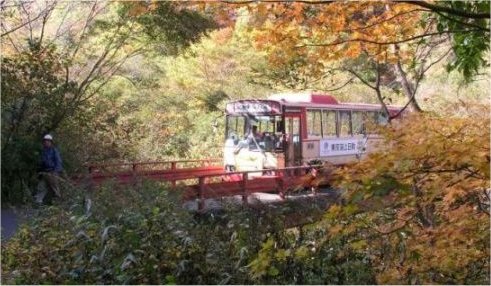
途中の米子橋は重量制限のため、乗客はバスを降り徒歩で渡る


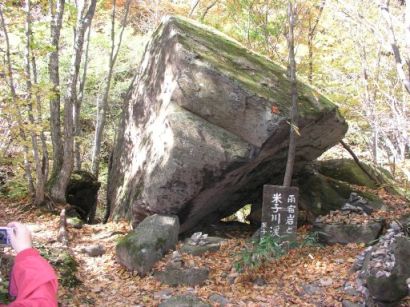
この二つの滝が有名なのは、日本有数の「夫婦滝」のためと言われ、男滝は「権現滝」で、 水量が多く真っ直ぐな直瀑。女滝は「不動滝」で、水量が少なく霧状に流れる落ちる姿が女性的。最近では「恋人滝」とも言われている 一帯は山岳信仰の聖地とされてきていて、この滝は古くから修験者の禊ぎの場とされ、夏になると行者の姿が見られる
権現滝と不動滝という二つの滝からなる。いずれも直瀑で、落差は権現滝が75メートル、不動滝が85メートルある これだけの落差の滝が二つ並ぶというのは日本国内において珍しい。両滝の水は周辺の渓流を合流させ、 須坂市内を北西へと流れ、千曲川(長野県内における信濃川の呼称)に注ぐ
滝の下にある米子不動尊は、「米子のお不動さん」として庶民の信仰を集める日本三大不動尊の一つで、 今でも修験者の水行の霊場としても知られています。







米子鉱山は、標高1500から1600メートル付近に位置し、山の奥深い山峡に位置したことから、 昭和9年に中外鉱業株式会社が本格的な営業採掘を始め、昭和11年には中外硫黄株式会社となり操業を行った。 このころ時代は、日清、日露、世界大戦を迎え、硫黄が爆破火薬の材料にされたことから生産量が増え月産1200tを生産し、 鉱山関係者1500人が生活していたと言われる。 戦後を迎え硫黄の需要が減少、生産コストも高くなり、石油化学工業の発展にも影響され、年々後退し昭和35年に閉山された。