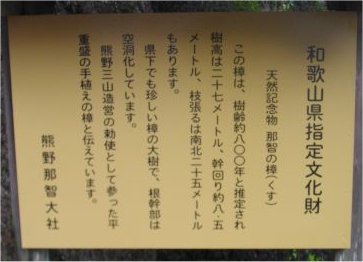熊野那智大社の社殿は現在、那智の滝から離れた高台にあるが、かつては大滝の近くあったらしい、
仁徳天皇5年(317年)に現在地に遷されたと伝えられる
 境内には正面に五殿がある。 右から四つ目の御社殿が、熊野夫須美大神(イザナミノミコト)をまつるお宮でひときわ大きい、
各社殿とも熊野造りで正面の簾の奥は蔀戸で、左側には格子戸があります。殿内は外陣・内陣の二つに区切られている
外に廻廊があり、正面に木階があり、床下に腰袴がある
境内には正面に五殿がある。 右から四つ目の御社殿が、熊野夫須美大神(イザナミノミコト)をまつるお宮でひときわ大きい、
各社殿とも熊野造りで正面の簾の奥は蔀戸で、左側には格子戸があります。殿内は外陣・内陣の二つに区切られている
外に廻廊があり、正面に木階があり、床下に腰袴がある

 参道の長い石段の上は、右に青岸渡寺があり、左は朱の大鳥居と大社の境内が続く
熊野那智大社の社殿および境内地は、ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の構成資産の一部
参道の長い石段の上は、右に青岸渡寺があり、左は朱の大鳥居と大社の境内が続く
熊野那智大社の社殿および境内地は、ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の構成資産の一部
 境内には正面に五殿がある。 右から四つ目の御社殿が、熊野夫須美大神(イザナミノミコト)をまつるお宮でひときわ大きい、
各社殿とも熊野造りで正面の簾の奥は蔀戸で、左側には格子戸があります。殿内は外陣・内陣の二つに区切られている
外に廻廊があり、正面に木階があり、床下に腰袴がある
境内には正面に五殿がある。 右から四つ目の御社殿が、熊野夫須美大神(イザナミノミコト)をまつるお宮でひときわ大きい、
各社殿とも熊野造りで正面の簾の奥は蔀戸で、左側には格子戸があります。殿内は外陣・内陣の二つに区切られている
外に廻廊があり、正面に木階があり、床下に腰袴がある

 参道の長い石段の上は、右に青岸渡寺があり、左は朱の大鳥居と大社の境内が続く
熊野那智大社の社殿および境内地は、ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の構成資産の一部
参道の長い石段の上は、右に青岸渡寺があり、左は朱の大鳥居と大社の境内が続く
熊野那智大社の社殿および境内地は、ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の構成資産の一部